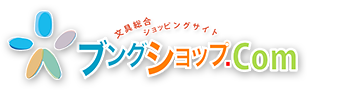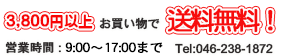文房具の代名詞、それは鉛筆!

4月…とうとう終わってしまいましたね。
新しいことがスタートする4月は1年のうちで1番自分の名前を書くなぁ…なんて思ったりしませんでしたか?✐
…ということで今日は何かと「文字」に触れる機会が多いこの時期にちなんで、また書くときに紙の上をなぞる感触が好きな私の独断で「鉛筆」について書いてみたいと思います。
「鉛筆」…読み方は「えんぴつ」…(そんなこと知ってるわ!!って?…はい。お静かに…)
「鉛筆」の文字の「筆」の前に「鉛」という字が入ってますね。
「原料に入ってるからでしょ!!」と誰もが想像つくと思いますが当たりです。
ではなぜ、昔は人の生活の身近にあった「炭」ではなく「鉛」なの?と思いませんでしたか?
(そんなことを思うのは私だけ…?!)
では、どのようにして人間と鉛筆の原料である「鉛」とが出会ったのかをザッと説明しちゃいます。
✐えんぴつのおいたち✐
今から458年前に【イギリスの国旗の絵文字】イギリスのボローデール鉱山で良質の黒鉛(こくえん)が発見されたそうです。
その黒鉛は黒くなめらかな性質だったので、こまかく切ったり、にぎりの部分をヒモで巻いたりして
筆記具として使われるようになったのが「鉛筆」の始まりだとか。
それは黒鉛を板状か棒状に削って板にはめ込む簡単なものだったそうです。
手が汚れないようにそのようにしたのだと思いますが、このときから鉛筆の芯は木と共にセットされていたんですね。
そのあともまだまだ鉛筆の改良は続きます。
この200年後には黒鉛の粉を硫黄などで固めた芯(しん)を作り、235年には硫黄の代わりに粘土に黒鉛を混ぜたのを焼き固めて芯を作ったそうです。
さらにこの混合の比率を変えれば芯の硬度が変化することを発見したというから驚きです。
今現在も基本的には、このコンテの方法でえんぴつの強度が決まり芯は作られているそうですが 何とも!
これは人間が字や何かを書くことに必要性を感じてるからこその開発であったことが感じられますね。
なんだか鉛筆がとっても愛しく感じてきませんか?

鉛筆はとっても奥深いのですが、くどくなってしまうのでここからはちょっとしたクイズ&豆知識を書いていきます。
✐鉛筆の豆知識✐
✐Question①✐
今、生活の身近にある筆記具の中で一番長く書くことができるのは何だと思いますか?
そうです。鉛筆なんです✐
なんと!!
機械を使って削らないで芯を使うとフルマラソンの42.195kmよりも長い約50kmも書けるそうです。
50kmの距離を歩こうとしたら人間の歩行速度は、時速4キロと言われているので休憩なしで12時間30分の距離を書けるということになります。
気が遠くなる距離を鉛筆1本で書けてしまうってことですね。
参考までに他の筆記具と比較してみると油性ボールペン約1.5KM シャープペン約240M 蛍光ペン約150Mだそうです。
鉛筆ダントツです。
✐Question②✐
鉛筆には六角形が多いのは何故だと思いますか?
それは転がらないため、持ちやすいためだそうです。
鉛筆を握ったとき、必ず親指・人差し指・中指の3点で押さえるので3の倍数である必要があるからだそうです。
いかに転ばせてはいけない環境で(授業とか)使うことが多いなども、ちゃんと考えられているのですね。
ここでふと「でも色えんぴつは丸軸が多いと思うのだけど…」と思った人いませんか?
よく気づきましたね☆
気づいたあなたは文具好きですか? そうだとしたら私は嬉しいです。
色えんぴつは文字を書くだけでなく絵を描くために使ったり、色々な持ち方をして使うことが多いので指あたりのよい丸軸にしているそうです。
✐Question③✐
1本の木…たとえば直径2メートル、高さ20メートルの木からは何本の鉛筆がとれると思いますか?
すぐには想像がつかないのですが75万から80万本もえんぴつがとれるそうです。
【いろんな鉛筆・色鉛筆をテーブルいっぱいに広げた写真とか】
なんだか鉛筆が愛おしく懐かしくなってきませんか?
そういう人のために「鉛筆のような書き味」のシャープペンもありますよ。
ジャン!! こちらです↓
では、ここでQuestionは終わりにして日本で一番古いと言われている鉛筆についてちょっと書きますね。
なんと!!
静岡県の徳川家康公を御祭神とする「久能山東照宮博物館」に徳川家康の遺品(いひん)として1本だけ展示されてるそうです✐
記録が残っていないので、どのような経緯で日本に渡ってきたか分かりませんが、その当時、属領(ぞくりょう)であった フィリピンから家康に献上(けんじょう)されたものであろうといわれています。
「うんこ漏らしの家康」と知られている(家康さんごめん。まだ私、漏らすほどの恐怖を経験したことない)「家康さん」が 現在も残存する最古の【✐】鉛筆を使っていたとは…。
何を思い使っていたのか思いをはせてしまいますね。
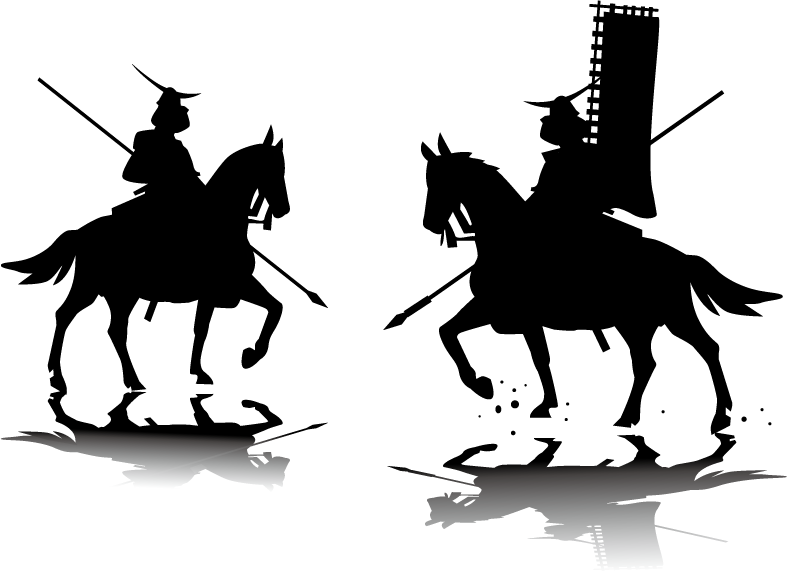
この博物館には家康公の日常品(手沢品)や徳川歴代将軍の武器・武具が充実している博物館なので観光がてらに寄ってみても良いですね。
(鉛筆の歴史は古い…なのに隅に追いやられてる感ある鉛筆ってかわいそう←こころの声)
では、最後に私が勝手に思っている文具の三角関係についてちょっとだけ…
登場文具の紹介をします。
- 字を覚えるときにはモテはやされるのに、いつしか存在が薄くなっていく悲しい存在の鉛筆✐
- 常に進化し使う人のニーズによって使い分けられるノート
- 人間が極力、力と気を使わず楽に消せることを追求され続けてる消しゴム
感の鋭い人は私が何を書こうとしてるか分かっちゃいましたね。
まずは今日ここまで書いてきた「✐鉛筆✐」がどのようにして書けるのか…。
それは①芯が紙に当たる→②芯が砕ける→③砕けた芯に含まれている「黒鉛」が「紙の繊維」に絡みつくからだそうです。 !!!!!
!これを知ったとき私の癖である妄想が始まってしまったのでありますが…。
なめらかに書かけることを追求するノートと、そのノートに絡んで絡みついて文字や絵を残したい鉛筆の黒鉛、そこへ登場するのが、この光景を遠目に見ていたかどうかは知らないが重要な存在の消しゴム。
この消しゴムの存在は鉛筆の黒鉛にとってとても大きく、消しゴムが現れ接触した途端、ホイホイと 消しゴムにくっついて黒鉛はノートから離れてしまうのだ。
ならば鉛筆と消しゴムは相思相愛か?!と思いきや、いやいや…そう簡単ではなくノートも消しゴムも
鉛筆を軽く消せるノートとair-in消しゴムが存在するのだ。
これは商品のほんの一部のことなのだけど、「素晴らしき三角関係だ!!!!!」と私は思ったのであります。
…と同時に心の中で「鉛筆がんばれ!! シャーペンよりも鉛筆が好きだ!! 」だけど実は鉛筆よりもボールペンが好きなのだ!!(鉛筆ごめん!!)
ちょっと話が脱線してしまったので、ちょっと真面目に戻って、少しおさらいしながらどのようにして 鉛筆の黒鉛が紙からはがれるのかを説明します。
鉛筆の黒鉛は紙に絡まって文字などを残すのですが、黒鉛は紙よりも消しゴムの方がくっつきやすく くっついたら最後、消しゴムのカスに包まれて黒鉛は紙からはがされるらしいのです。
すごいですね…それぞれの役割分担を最高の状態に近づけるように商品開発されていく日本の文具業界。
私事になってしまいますが3年ほど前、海外の友だちが日本のシャープペン・トンボのモノグラフを使って字を消そうと消しゴムを出したときに感動して言った「Japanese technology」が忘れられません。
すごいですよね。
しつこいけど日本の文具は素晴らしいです。
最後の方は「鉛筆」のことではなく「消しゴム」のことについて書いてしまいましたが これからも個人だけでなく世界が注目してる日本の文具について書いていきたいと思います。
楽しみに待っていてね…
(追伸…ペタペタ「確かに書いた文字に消しゴムを押し付けただけで少し字が消えるな…」こころの声)
返信コメント
投稿はありません